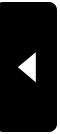2006年01月25日
捕食行動とフラグ(補足)。
前回は、
食行動は刺激によって起こる。と書きましたが、今回は蛇足補足です。
そもそも、刺激というのは、主に視覚で捉えた事象に対し、体内で様々な物質が分泌される事を指します。
その結果として、色々な行動が起こるわけです。
例えば、
梅干を口の中に入れると唾液が分泌されます。
→これが生得的行動です。
上の文章を見て、思わず口の中に唾液が出た(036は出ました^^)
→これが習得的行動です。
前者は、生まれつき持っている機能。
後者は、成長していく過程で得た経験からきた行動です。
さて、肝心の捕食行動です。
食行動は刺激によって起こる。と書きましたが、今回は
そもそも、刺激というのは、主に視覚で捉えた事象に対し、体内で様々な物質が分泌される事を指します。
その結果として、色々な行動が起こるわけです。
例えば、
梅干を口の中に入れると唾液が分泌されます。
→これが生得的行動です。
上の文章を見て、思わず口の中に唾液が出た(036は出ました^^)
→これが習得的行動です。
前者は、生まれつき持っている機能。
後者は、成長していく過程で得た経験からきた行動です。
さて、肝心の捕食行動です。
捕食行動に至る刺激を与える道具として、釣り人は生き餌、もしくは疑似餌を使用します。
もちろん、036はフライを使います。フライフィッシャーですから^^
フライは、外見的な特徴と、使用目的に応じた特長があります。
その1つ1つに、魚に刺激を与えるファクターがあります。
さらに、アクションをつける(何もしないのもアクションですね)事も、有効な刺激です。
フライフィッシングの用語に、「ドラグフリー」という言葉があります。
要は、フライが水面上を、自然に流れるためのテクニックなのですが、これが忙しい。
ドラグというのは水の流れのことです。
面積が大きいほど、流されやすくなります。
フライラインにドラグが掛かって流されると、フライも動きが不自然になってしまいます。
そうならないように、ラインをコントロールしなければなりません。
このライン操作を「メンディング」と呼びます。
っと閑話休題。ドラグの話でした。
何故、ドラグフリーが良いか?という話なのですが、ここでようやくフラグが出てきます。
魚が食べている→フラグが立っている、と考えるならば
フライを普段食べているエサに近付けるためには、ドラグフリーが前提。
魚にとって、流下物の動きとはドラグフリーなわけですから(当たり前)。
他のファクターも普段のエサと同じフラグが立てば、捕食してくる筈です。
当然、時間的な要素など、周囲の環境によってフラグも変化します。
また、魚のコンディションも個体差があるため、一概には言えないかもしれません。あくまで概論として書いています。
逆に、立ててはいけないフラグもあります。
つまり、魚に捕食行動をやめさせる行動のフラグを立てる。
・・・まわりくどいな。
単純に、警戒フラグにしましょう。
このフラグを立てると、ほぼ釣れなくなります。
要因は、釣り人の行動に因るところ大です。
ですが、他の生物の行動なども考えられます。
釣り場での行動が、釣果に影響するのはこのためですね^^
(036はこの点、反面教師です^^;)
この状態、スレとは若干違うと考えています。
スレる、というのは、捕食フラグが極端に減った状態。
一方、警戒フラグは、捕食行動の非常停止状態。
ではないかと思います。
例えば、マラブーを引っ張りで釣ったと仮定します。
・魚が途中までは追いかけたが、なぜか食いついてこない、
→スレている。
・魚が、マラブーを見た途端に逃げてしまった、
→警戒フラグが立っている。
という感じでしょうか?
*追記*
スレの状態について。
・途中まで追いかけた。という事は、捕食行動に入っている。
→(途中で)捕食をやめた。という事は、スイッチが切れたわけではなく、他の行動のフラグが立った。そう考えたほうが良さそうです。
つまり、スレと警戒フラグは同一。ということなのでしょうか?
もしかしたら、警戒行動も段階的に分かれているのかも。
コンディショングリーンからレッドに変わるように、魚の体中でも、見えない変化があるのかもしれませんね。
もちろん、036はフライを使います。フライフィッシャーですから^^
フライは、外見的な特徴と、使用目的に応じた特長があります。
その1つ1つに、魚に刺激を与えるファクターがあります。
さらに、アクションをつける(何もしないのもアクションですね)事も、有効な刺激です。
フライフィッシングの用語に、「ドラグフリー」という言葉があります。
要は、フライが水面上を、自然に流れるためのテクニックなのですが、これが忙しい。
ドラグというのは水の流れのことです。
面積が大きいほど、流されやすくなります。
フライラインにドラグが掛かって流されると、フライも動きが不自然になってしまいます。
そうならないように、ラインをコントロールしなければなりません。
このライン操作を「メンディング」と呼びます。
っと閑話休題。ドラグの話でした。
何故、ドラグフリーが良いか?という話なのですが、ここでようやくフラグが出てきます。
魚が食べている→フラグが立っている、と考えるならば
フライを普段食べているエサに近付けるためには、ドラグフリーが前提。
魚にとって、流下物の動きとはドラグフリーなわけですから(当たり前)。
他のファクターも普段のエサと同じフラグが立てば、捕食してくる筈です。
当然、時間的な要素など、周囲の環境によってフラグも変化します。
また、魚のコンディションも個体差があるため、一概には言えないかもしれません。あくまで概論として書いています。
逆に、立ててはいけないフラグもあります。
つまり、魚に捕食行動をやめさせる行動のフラグを立てる。
・・・まわりくどいな。
単純に、警戒フラグにしましょう。
このフラグを立てると、ほぼ釣れなくなります。
要因は、釣り人の行動に因るところ大です。
ですが、他の生物の行動なども考えられます。
釣り場での行動が、釣果に影響するのはこのためですね^^
(036はこの点、反面教師です^^;)
この状態、スレとは若干違うと考えています。
スレる、というのは、捕食フラグが極端に減った状態。
一方、警戒フラグは、捕食行動の非常停止状態。
ではないかと思います。
例えば、マラブーを引っ張りで釣ったと仮定します。
・魚が途中までは追いかけたが、なぜか食いついてこない、
→スレている。
・魚が、マラブーを見た途端に逃げてしまった、
→警戒フラグが立っている。
という感じでしょうか?
*追記*
スレの状態について。
・途中まで追いかけた。という事は、捕食行動に入っている。
→(途中で)捕食をやめた。という事は、スイッチが切れたわけではなく、他の行動のフラグが立った。そう考えたほうが良さそうです。
つまり、スレと警戒フラグは同一。ということなのでしょうか?
もしかしたら、警戒行動も段階的に分かれているのかも。
コンディショングリーンからレッドに変わるように、魚の体中でも、見えない変化があるのかもしれませんね。
Posted by 036 at 22:48│Comments(2)
│釣”孝”記
この記事へのコメント
こんにちわ、guitarbirdです
東京にいた頃、FFやってる友達の「運転手」として何度か同行しましたが、
友達が飽きると竿を借りて遊んでました。
その時やはり、どうしたら自然に見えるように流せるか、
ということを考えました。考えただけですが(笑)。
ちなみに30分ほどでウグイを4、5釣りました。
なお私は、FFに関しては、その時以来進歩してません・・・
東京にいた頃、FFやってる友達の「運転手」として何度か同行しましたが、
友達が飽きると竿を借りて遊んでました。
その時やはり、どうしたら自然に見えるように流せるか、
ということを考えました。考えただけですが(笑)。
ちなみに30分ほどでウグイを4、5釣りました。
なお私は、FFに関しては、その時以来進歩してません・・・
Posted by guitarbird at 2006年01月27日 16:07
guitarbirdさん、こんばんわ。
フライフィッシングでは、「考える」という事が1番大事だと思います。
道楽ですから、プロセスも楽しまないと^^
30分で4,5匹とは。
絶対に才能ありますよ!!
(お世辞じゃないですよ、と釣ってみる^^)
フライフィッシングでは、「考える」という事が1番大事だと思います。
道楽ですから、プロセスも楽しまないと^^
30分で4,5匹とは。
絶対に才能ありますよ!!
(お世辞じゃないですよ、と釣ってみる^^)
Posted by 036 at 2006年01月27日 19:28
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。