2006年07月03日
あるロマン派の一生(解明編)。
さて、前回、「ます」の誕生の背景については分かったものの、新たな疑問が生まれました。つまり、
「ます」5重奏の前身である、歌曲「ます」について
です。
この歌曲「ます」がどのようにして生まれたかについてですが、それはシューベルトの作曲方法と密接な関わりがありました・・・。
歌曲「ます」が作曲された当時、シューベルトはかなりビンボーで、五線譜さえも満足に買うことが出来ませんでした。そんな彼に暖かい援助の手を差し伸べたのは、年長の友人たち。
彼らは、シューベルトのために楽譜や、作曲のイマジネーションが湧きそうな芸術的な資料を買ってあげたり、旅行(前回参照)に誘ったりしました。
そして、その資料の中に、歌曲「ます」が誕生する契機があったのです。 続きを読む
「ます」5重奏の前身である、歌曲「ます」について
です。
この歌曲「ます」がどのようにして生まれたかについてですが、それはシューベルトの作曲方法と密接な関わりがありました・・・。
歌曲「ます」が作曲された当時、シューベルトはかなりビンボーで、五線譜さえも満足に買うことが出来ませんでした。そんな彼に暖かい援助の手を差し伸べたのは、年長の友人たち。
彼らは、シューベルトのために楽譜や、作曲のイマジネーションが湧きそうな芸術的な資料を買ってあげたり、旅行(前回参照)に誘ったりしました。
そして、その資料の中に、歌曲「ます」が誕生する契機があったのです。 続きを読む
2006年07月03日
あるロマン派の一生(旅情編)。
それでは再開。前回の話は、こちらからどうぞ。
さて、シューベルトが友人に連れられてやってきたのは、ウィーンの西部にある、リンツという小都市。1819年の夏でありました。
ここで、彼はパウムガルトナーという人物の家へ招かれます。
パウムガルトナーとはどんな人物だったかというと、鉱山の経営者で、自身もチェロ奏者であり、シューベルトのファンでもありました。
ようするにお金持ち。しかも教養人だったわけです。
どのくらい滞在したかは分かりませんが、演奏会を開いたりしたようです。
ちなみに当時シューベルトは22歳くらい。
すでに教員を辞め、貴族様の音楽の先生をやっていました。
いよいよ、世間に認知され始めましたね。
公的にも、コンサートを依頼されるなど活躍の場が広がっていきます。
さて、滞在中にパウムガルトナーから、ある依頼を受けたシューベルト。
その内容は、といいますと・・・。 続きを読む
さて、シューベルトが友人に連れられてやってきたのは、ウィーンの西部にある、リンツという小都市。1819年の夏でありました。
ここで、彼はパウムガルトナーという人物の家へ招かれます。
パウムガルトナーとはどんな人物だったかというと、鉱山の経営者で、自身もチェロ奏者であり、シューベルトのファンでもありました。
ようするにお金持ち。しかも教養人だったわけです。
どのくらい滞在したかは分かりませんが、演奏会を開いたりしたようです。
ちなみに当時シューベルトは22歳くらい。
すでに教員を辞め、貴族様の音楽の先生をやっていました。
いよいよ、世間に認知され始めましたね。
公的にも、コンサートを依頼されるなど活躍の場が広がっていきます。
さて、滞在中にパウムガルトナーから、ある依頼を受けたシューベルト。
その内容は、といいますと・・・。 続きを読む
2006年06月22日
あるロマン派の一生(青春編)。
今回はシューベルトの人生について。
え?ますはどうした?
まあまあ、慌てない慌てない。
ますが生まれた背景には、彼の作曲スタイル。
はては人生そのものと大きく関わりがあるのです。
それでは、まずは生い立ちから。
フランツ・ペーター・シューベルト(Franz Peter Schubert)は、1797年にウィーンの音楽一家のもとに生まれました。生まれた時から音楽に親しむ環境に居たシューベルト。その才能を伸ばすべく、11歳で音楽の専門学校に入学します。
この頃の学校というのは、現在とは主旨が違っていまして、生徒の自立のための教育を目標にしていたわけではなく、あくまで音楽の才能を伸ばす事だけを主眼にしておりました(特に声楽)。
ぶっちゃけ、生徒というよりは、一つの楽器としてみていた節があります。
ここでシューベルトは生涯の友を多く獲得する事が出来ました。
じつはビンボーだったシューベルト。
そんな彼を見かねて、友人たちは援助を惜しまなかったそうです。
そして、この関係は彼が死ぬまで続きました。
在学中から、すでに作曲を始めていたシューベルト。
15歳ころに声変わりのため学校を辞めます。
すぐに就職活動開始。 続きを読む
え?ますはどうした?
まあまあ、慌てない慌てない。
ますが生まれた背景には、彼の作曲スタイル。
はては人生そのものと大きく関わりがあるのです。
それでは、まずは生い立ちから。
フランツ・ペーター・シューベルト(Franz Peter Schubert)は、1797年にウィーンの音楽一家のもとに生まれました。生まれた時から音楽に親しむ環境に居たシューベルト。その才能を伸ばすべく、11歳で音楽の専門学校に入学します。
この頃の学校というのは、現在とは主旨が違っていまして、生徒の自立のための教育を目標にしていたわけではなく、あくまで音楽の才能を伸ばす事だけを主眼にしておりました(特に声楽)。
ぶっちゃけ、生徒というよりは、一つの楽器としてみていた節があります。
ここでシューベルトは生涯の友を多く獲得する事が出来ました。
じつはビンボーだったシューベルト。
そんな彼を見かねて、友人たちは援助を惜しまなかったそうです。
そして、この関係は彼が死ぬまで続きました。
在学中から、すでに作曲を始めていたシューベルト。
15歳ころに声変わりのため学校を辞めます。
すぐに就職活動開始。 続きを読む
2006年06月20日
ますのはなし。
関東地方も入梅(これで「つゆいり」って読むんですね!)です。
最近、フライフィッシングの記事ばかり書いていることに気付きました。
ある意味当然?
036自身も、ネタがあるうちはこれでいいやと考えていたのですが・・・。
なぜか周りの方から
『フライフィッシングの記事ばかりで面白くない』
という賞賛の声がチラホラと・・・。
それでは、というわけでもないですが、今回は思い切って別の話を。
何にしようか思案したのですが、ますの話にしました。
え?ます?
(1)

また魚の話かよ。
・・・いえ違いマス。
正確には
ピアノ五重奏曲 イ長調 D667, Op.114
なんのこっちゃ? 続きを読む
最近、フライフィッシングの記事ばかり書いていることに気付きました。
ある意味当然?
036自身も、ネタがあるうちはこれでいいやと考えていたのですが・・・。
なぜか周りの方から
『フライフィッシングの記事ばかりで面白くない』
という
それでは、というわけでもないですが、今回は思い切って別の話を。
何にしようか思案したのですが、ますの話にしました。
え?ます?
(1)

また魚の話かよ。
・・・いえ違いマス。
正確には
ピアノ五重奏曲 イ長調 D667, Op.114
なんのこっちゃ? 続きを読む
2005年09月04日
犬のしつけ、飼い主のしつけ。
今日は、初めて「しつけ教室」に(みゅうず抜きで)行ってきました。
前半は座学で、後半は実際に訓練士による実演という形でした。
開始が10時からという事だったんですが、036は前日の深酒がきいたのか?起きたのが9時50分!!慌てて現地に行ったら、まだ始まってないようで一安心でした(^^;)
それから知り合いの方としばし談笑、講義開始は10時30分頃からでした。
今回はシェパードのオーナーのための講義なので、座学はシェパードのスタンダードとは、という内容でした。みゅうずはシェルティーなのですが、牧羊犬という括りで見ればあまり変わらないし、興味半分で参加しました。
内容は、血統書の見方に始まり、いかに良いシェパードを将来に残すか、そもそも良いシェパードの条件て何よ?という話と、現在飼っているシェパードの問題行動について、なんで起こるのか?どうすれば改善されるのか?といった話でした。
昼食も先生と一緒に食べたんですが、たまたま席が036の隣だったので、色々質問できて楽しかったです。親父ギャグはサムかったですが・・・(失礼な)
午後は実際に犬の問題行動を見ながら、(犬より飼い主に)指導をしてもらいました。訓練士はオーラが違うなぁ・・・。
ここで036が感じたのは、叱りながらしつけるのは、とても難しい。とくに罰を与えるしつけは、036には全然出来なさそうです。例えば、他の犬にケンカを売る直前に制止するなんて、修羅場経験ゼロの036には不可能だな、と思いました。
今回は、この間きいた講義の内容を補完する意味で、大変参考になりました。しかも訓練士が実際に犬をしつける現場は見たことが無かったので、面白かったです(不謹慎かもしれませんが)。
訓練士の罰の与え方が、象使いのやり方にそっくりだったのにはビックリしましたが、これも当然かも。
前半は座学で、後半は実際に訓練士による実演という形でした。
開始が10時からという事だったんですが、036は前日の深酒がきいたのか?起きたのが9時50分!!慌てて現地に行ったら、まだ始まってないようで一安心でした(^^;)
それから知り合いの方としばし談笑、講義開始は10時30分頃からでした。
今回はシェパードのオーナーのための講義なので、座学はシェパードのスタンダードとは、という内容でした。みゅうずはシェルティーなのですが、牧羊犬という括りで見ればあまり変わらないし、興味半分で参加しました。
内容は、血統書の見方に始まり、いかに良いシェパードを将来に残すか、そもそも良いシェパードの条件て何よ?という話と、現在飼っているシェパードの問題行動について、なんで起こるのか?どうすれば改善されるのか?といった話でした。
昼食も先生と一緒に食べたんですが、たまたま席が036の隣だったので、色々質問できて楽しかったです。親父ギャグはサムかったですが・・・(失礼な)
午後は実際に犬の問題行動を見ながら、(犬より飼い主に)指導をしてもらいました。訓練士はオーラが違うなぁ・・・。
ここで036が感じたのは、叱りながらしつけるのは、とても難しい。とくに罰を与えるしつけは、036には全然出来なさそうです。例えば、他の犬にケンカを売る直前に制止するなんて、修羅場経験ゼロの036には不可能だな、と思いました。
今回は、この間きいた講義の内容を補完する意味で、大変参考になりました。しかも訓練士が実際に犬をしつける現場は見たことが無かったので、面白かったです(不謹慎かもしれませんが)。
訓練士の罰の与え方が、象使いのやり方にそっくりだったのにはビックリしましたが、これも当然かも。
2005年08月28日
犬の求める飼い主って?その3
今回で(一応)最終回です。
1回目で、行動は刺激によって起きることを
2回目で、刺激の種類と犬に与える影響を書きましたが、今回は
「行動と感情の結びつきについて」
行動と感情は密接にリンクしており、お互いに影響を与え合っています。
相手の感情を考えないと、せっかくの強化子が役に立ちません。
例>
お腹がいっぱいのときにおやつをあげてもうれしくない
→こういう事ですね。
・捕食行動(生得的行動・感情は関与していない)をしたときに
成功→うれしい、満足
失敗→不満、失望
という感情が発生します。
不安や恐怖の感情は、4つの「F(で始まる行動)」をとらせます。
→FIGHT(闘争)、FLIGHT(逃走)、FREEZE(動かない)、FLIRT(交渉)
そして、この行動をとることにより、感情が安定するわけです。
*不安や恐怖を感じているときは、強化子を与えてはいけない!!
→飼い主がなだめたり、かばったりする事で、その行動が増加、形成されてしまう(刺激は強化子を与えているのと一緒)。
問題行動の原因は、ほぼ100%恐怖や不安が関与している。
しかし、そのときに飼い主がその行動を助長していたら・・・。
では飼い主はどうすればよいのか?というと、不安とは関係ない行動をとらせれば良いんです。他の行動をとった犬は、必然的に問題行動をとれなくなります。
つまり、本当の躾とは、犬の感情をコントロールする事だといえます。
例>
病院の診療台の上で不安になっている。
→飼い主がやることは、体を撫でるのではなく、「おすわり」と行動をとらせること。
最後に、036は犬と人間はタテの関係だと思っていました。だって、犬同士は明確な上下関係が築かれているって、どの本を読んでも書いてあったし。しかし、実際は犬同士の上下関係は、あまり明確ではないそうです。
さらに、犬の躾で有名なのが、口をぎゅっと押さえつけて、クゥ~ンと言うまで離さない、というもの。主従関係をはっきりさせるそうです。036はやったことが無かった(口の中に指を突っ込んだことはある)のですが、この躾をした結果、病院で診察しようとした獣医さんに、噛みつく犬が増えただけで、意味が無い(むしろ逆効果)。同じように、首根っこを摑まえて振り回すというのもやめたほうが良いそうです。
動物というのは、個体としてのミクロな視点と、種としてのマクロな視点で捉えないと、全体像が見えてこないような気がします。長い年月をかけて、ある用途のためだけに人間が改良してきたものを、ほとんどの人がまったく別の用途で飼っています。そりゃあ少しは無理が出るよ、と036は思ってしまいます。人間にだって現代の変化のスピードは早いのに、犬にとっては・・・。
*まとめ
036は、みゅうずの感情を理解し、コントロールすることで問題行動の抑止をする方法を覚えよう。って事でお終いです。まだまだ理解してない部分も多いし、舌足らずな文章なので、時間があれば更新します。
1回目で、行動は刺激によって起きることを
2回目で、刺激の種類と犬に与える影響を書きましたが、今回は
「行動と感情の結びつきについて」
行動と感情は密接にリンクしており、お互いに影響を与え合っています。
相手の感情を考えないと、せっかくの強化子が役に立ちません。
例>
お腹がいっぱいのときにおやつをあげてもうれしくない
→こういう事ですね。
・捕食行動(生得的行動・感情は関与していない)をしたときに
成功→うれしい、満足
失敗→不満、失望
という感情が発生します。
不安や恐怖の感情は、4つの「F(で始まる行動)」をとらせます。
→FIGHT(闘争)、FLIGHT(逃走)、FREEZE(動かない)、FLIRT(交渉)
そして、この行動をとることにより、感情が安定するわけです。
*不安や恐怖を感じているときは、強化子を与えてはいけない!!
→飼い主がなだめたり、かばったりする事で、その行動が増加、形成されてしまう(刺激は強化子を与えているのと一緒)。
問題行動の原因は、ほぼ100%恐怖や不安が関与している。
しかし、そのときに飼い主がその行動を助長していたら・・・。
では飼い主はどうすればよいのか?というと、不安とは関係ない行動をとらせれば良いんです。他の行動をとった犬は、必然的に問題行動をとれなくなります。
つまり、本当の躾とは、犬の感情をコントロールする事だといえます。
例>
病院の診療台の上で不安になっている。
→飼い主がやることは、体を撫でるのではなく、「おすわり」と行動をとらせること。
最後に、036は犬と人間はタテの関係だと思っていました。だって、犬同士は明確な上下関係が築かれているって、どの本を読んでも書いてあったし。しかし、実際は犬同士の上下関係は、あまり明確ではないそうです。
さらに、犬の躾で有名なのが、口をぎゅっと押さえつけて、クゥ~ンと言うまで離さない、というもの。主従関係をはっきりさせるそうです。036はやったことが無かった(口の中に指を突っ込んだことはある)のですが、この躾をした結果、病院で診察しようとした獣医さんに、噛みつく犬が増えただけで、意味が無い(むしろ逆効果)。同じように、首根っこを摑まえて振り回すというのもやめたほうが良いそうです。
動物というのは、個体としてのミクロな視点と、種としてのマクロな視点で捉えないと、全体像が見えてこないような気がします。長い年月をかけて、ある用途のためだけに人間が改良してきたものを、ほとんどの人がまったく別の用途で飼っています。そりゃあ少しは無理が出るよ、と036は思ってしまいます。人間にだって現代の変化のスピードは早いのに、犬にとっては・・・。
*まとめ
036は、みゅうずの感情を理解し、コントロールすることで問題行動の抑止をする方法を覚えよう。って事でお終いです。まだまだ理解してない部分も多いし、舌足らずな文章なので、時間があれば更新します。
ここまで読んでくれた方(いらっしゃいましたら)お疲れ様でした。
2005年08月28日
犬の求める飼い主って?その2
今回は、習得的行動が、どのように形成されるかを書きます。長文です。
*強化子と罰子について。
・強化子とは、犬にプラスの感情をもたらす刺激のこと。
強化子を与える(と専門用語では言います)と、その行動は増加します。
・罰子とは、犬にマイナスの感情をもたらす刺激のことです。
罰子が増加すると、恐怖症やパニック、受動的攻撃などの問題行動が、起こることになります。
分かりにくいので、例題で説明します。
例1>
「おすわり」を覚えさせるのに、出来たときのご褒美に、おやつを与えた。
→「おすわり」という行動に、「おやつ」という強化子を与えることによって、その行動が形成されていくわけですね。
例2>
仔犬の頃に、大型犬に襲われてしまい、それからは普通の犬を見ただけで怖がる。
→社会化期(4週齢~14週齢・犬種、血統で変わる)の経験は特に影響が大きく、トラウマとなってしまいます。経験が罰子になってしまったわけです。
前回書きましたが、犬は似たような刺激で同じ行動を起こし、最初は大きい犬だけ怖がっていたのがエスカレートして、犬を見ただけで怖いと思う様になってしまったわけです。
例3>
「甘噛み」がひどく、最初は噛んでくるたびに注意していたが、面倒なため時々しか注意しなくなった。しかし全然直らない。
→「甘噛み」は、つまらない、寂しい時にも起きます。このときに飼い主がアクションを起こすと、仔犬の不安を取り去ることになり、強化子として作用します。つまり仔犬は甘噛みをすると構ってくれると学習するわけです。
*徐々に強化子を減らすことは、行動を持続させ、形成させます。習得的行動の躾は、毎回おやつをあげるより、慣れてきたら徐々におやつをあげる回数を減らしたほうが、犬に緊張感が生まれて上手くいきます。
この行為を、オペラント条件付けといいます。
躾の話が出たので補足。罰についてです。
例4>
チョークチェーンを使った躾は、最初に罰を与え、その後に強化子を与えていく
→古典的方法といわれているやり方です。しかし、罰を用いた躾は非常に難しく、飼い主と犬との関係を壊してしまう可能性があります。罰というのは、犬の感情をマイナス方向にコントロールするための装置です。しかし、最初からマイナスの感情(不安、恐れ)を持っている犬には、不安を助長させる効果しかありません。なるべくやらないほうが良いようです。
個人的には、罰を用いた躾は、やりたくなかったのと、やる必要がなかったのでよく分かりませんが・・・。
では、困っている行動を減らすにはどうするか?
強化子を、完全に抜いてあげることです。100%です。仔犬の頃って、
無視するのが一番むずかしいんですけどね(笑)
このまま次回に続きます。次回が最終回の予定です。
*強化子と罰子について。
・強化子とは、犬にプラスの感情をもたらす刺激のこと。
強化子を与える(と専門用語では言います)と、その行動は増加します。
・罰子とは、犬にマイナスの感情をもたらす刺激のことです。
罰子が増加すると、恐怖症やパニック、受動的攻撃などの問題行動が、起こることになります。
分かりにくいので、例題で説明します。
例1>
「おすわり」を覚えさせるのに、出来たときのご褒美に、おやつを与えた。
→「おすわり」という行動に、「おやつ」という強化子を与えることによって、その行動が形成されていくわけですね。
例2>
仔犬の頃に、大型犬に襲われてしまい、それからは普通の犬を見ただけで怖がる。
→社会化期(4週齢~14週齢・犬種、血統で変わる)の経験は特に影響が大きく、トラウマとなってしまいます。経験が罰子になってしまったわけです。
前回書きましたが、犬は似たような刺激で同じ行動を起こし、最初は大きい犬だけ怖がっていたのがエスカレートして、犬を見ただけで怖いと思う様になってしまったわけです。
例3>
「甘噛み」がひどく、最初は噛んでくるたびに注意していたが、面倒なため時々しか注意しなくなった。しかし全然直らない。
→「甘噛み」は、つまらない、寂しい時にも起きます。このときに飼い主がアクションを起こすと、仔犬の不安を取り去ることになり、強化子として作用します。つまり仔犬は甘噛みをすると構ってくれると学習するわけです。
*徐々に強化子を減らすことは、行動を持続させ、形成させます。習得的行動の躾は、毎回おやつをあげるより、慣れてきたら徐々におやつをあげる回数を減らしたほうが、犬に緊張感が生まれて上手くいきます。
この行為を、オペラント条件付けといいます。
躾の話が出たので補足。罰についてです。
例4>
チョークチェーンを使った躾は、最初に罰を与え、その後に強化子を与えていく
→古典的方法といわれているやり方です。しかし、罰を用いた躾は非常に難しく、飼い主と犬との関係を壊してしまう可能性があります。罰というのは、犬の感情をマイナス方向にコントロールするための装置です。しかし、最初からマイナスの感情(不安、恐れ)を持っている犬には、不安を助長させる効果しかありません。なるべくやらないほうが良いようです。
個人的には、罰を用いた躾は、やりたくなかったのと、やる必要がなかったのでよく分かりませんが・・・。
では、困っている行動を減らすにはどうするか?
強化子を、完全に抜いてあげることです。100%です。仔犬の頃って、
無視するのが一番むずかしいんですけどね(笑)
このまま次回に続きます。次回が最終回の予定です。
2005年08月27日
犬の求める飼い主って?その1
今回は、なぜ犬は(問題といわれる)行動をとるのか?について、講義で学んだ内容と、036なりに考えたことを書いていきます。長文です。
まず、行動を科学的に捉えた場合、生得的行動と習得的行動の2種類に分類することができます。
生得的行動とは、生まれつき備わっている本能的行動のことで、生まれてすぐに出る行動と、成長する過程や大人になってから出てくるものがあります。また、遺伝情報によって決まってくるので、品種や血統による違いがあります。食行動や、性行動は生得的行動ですね。つまり、人間が管理するのは非常に難しいということです。
一方、習得的行動とは、経験を通じて得るもので、個体差(人生による差)が非常に大きくなります。
例1>
梅干を口に入れたときによだれが出るのが生得的行動
梅干を見ただけでよだれが出るのが習得的行動
例2>
牧羊犬は、羊を「眼」で誘導し、追い立てることが出来るが、チワワが羊を見ても、何もしない。
次に、行動を起こさせるものは何か?というと、刺激です。具体的には
・外的な刺激(視覚、聴覚、嗅覚など)
・内的な刺激(ホルモンの分泌、増減と、神経伝達物質による)
になります。
例>
神経伝達物質のセロトニンが不足すると、不安が増していく。
犬の場合は強迫障害(尻尾を噛もうとグルグル回ったりする)。
人の場合は強迫性障害(爪を噛み続けたり、何度も同じ事を確認したり)
*結論
犬がなぜその行動を引き起こしているか理解することが大事。
最初に何の刺激で起こったかを把握することが重要(犬は似た刺激にも同じ行動をしてしまうことが多く、徐々にエスカレートしていく)。
つまり、人間(飼い主)の義務は、行動の原因(何の刺激か)を突き止めて刺激は怖くない!!と犬に学習させることなんです。
そうすることで、問題行動の予防が出来るわけです。
とまあ、ここまでは比較的一般論に近いですね。次回は、どのように行動が形成されていくかについてを書く予定です。
まず、行動を科学的に捉えた場合、生得的行動と習得的行動の2種類に分類することができます。
生得的行動とは、生まれつき備わっている本能的行動のことで、生まれてすぐに出る行動と、成長する過程や大人になってから出てくるものがあります。また、遺伝情報によって決まってくるので、品種や血統による違いがあります。食行動や、性行動は生得的行動ですね。つまり、人間が管理するのは非常に難しいということです。
一方、習得的行動とは、経験を通じて得るもので、個体差(人生による差)が非常に大きくなります。
例1>
梅干を口に入れたときによだれが出るのが生得的行動
梅干を見ただけでよだれが出るのが習得的行動
例2>
牧羊犬は、羊を「眼」で誘導し、追い立てることが出来るが、チワワが羊を見ても、何もしない。
次に、行動を起こさせるものは何か?というと、刺激です。具体的には
・外的な刺激(視覚、聴覚、嗅覚など)
・内的な刺激(ホルモンの分泌、増減と、神経伝達物質による)
になります。
例>
神経伝達物質のセロトニンが不足すると、不安が増していく。
犬の場合は強迫障害(尻尾を噛もうとグルグル回ったりする)。
人の場合は強迫性障害(爪を噛み続けたり、何度も同じ事を確認したり)
*結論
犬がなぜその行動を引き起こしているか理解することが大事。
最初に何の刺激で起こったかを把握することが重要(犬は似た刺激にも同じ行動をしてしまうことが多く、徐々にエスカレートしていく)。
つまり、人間(飼い主)の義務は、行動の原因(何の刺激か)を突き止めて刺激は怖くない!!と犬に学習させることなんです。
そうすることで、問題行動の予防が出来るわけです。
とまあ、ここまでは比較的一般論に近いですね。次回は、どのように行動が形成されていくかについてを書く予定です。
2005年08月24日
犬の行動学(続き)。
本日、聴講してまいりました。
今回は、タイトルにもありますが
「犬の行動を科学的に理解する」という内容でした。
よく本などにある、犬の問題行動(無駄吠えや攻撃など)を
どうやってやめさせるか、といったハウツーものではなく、
どうして(問題といわれる)行動をとるのか?そのメカニズムに
ついての講義でした。
これが実に面白かった!!2時間の講義があっという間でした。
内容は近日中にアップします。目からウロコは間違いないですよ。
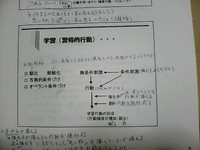
汚い字は036の手書きです・・・(汗)
今回は、タイトルにもありますが
「犬の行動を科学的に理解する」という内容でした。
よく本などにある、犬の問題行動(無駄吠えや攻撃など)を
どうやってやめさせるか、といったハウツーものではなく、
どうして(問題といわれる)行動をとるのか?そのメカニズムに
ついての講義でした。
これが実に面白かった!!2時間の講義があっという間でした。
内容は近日中にアップします。目からウロコは間違いないですよ。
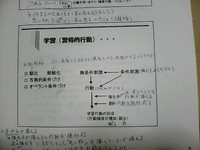
汚い字は036の手書きです・・・(汗)
2005年08月23日
犬の行動学。
FFとは全然関係ない話です。
明日は、「多摩獣医臨床研究会」の206回例会に行ってきます。
こう書くと、なにやらソッチ方面の仕事に就いてるみたいですが、
今回は公開講座という事で、門外漢の036も参加できるわけです。
しかも、遅い時間からのスタートなので、奉公人(丁稚?)の036には
とっても助かります。
この手のイベント?に参加(というより潜入かな)するのは初めて
なので、とても楽しみです。
学生の頃は「勉強なんかしなくても死なないじゃん」
とか思ってたのですが。
最近読んだ本に、相手とのコミュニケーションについて
「言葉が話せるかよりも、伝えたい事があるかどうかの方が重要だ」
という主旨の文章がありまして、感心しちゃいました。
そうか036は今が学びたい時期なんだ、と思ったわけです。
・・・この情熱が仕事に行かないのが036流、なんて。
明日は、「多摩獣医臨床研究会」の206回例会に行ってきます。
こう書くと、なにやらソッチ方面の仕事に就いてるみたいですが、
今回は公開講座という事で、門外漢の036も参加できるわけです。
しかも、遅い時間からのスタートなので、奉公人(丁稚?)の036には
とっても助かります。
この手のイベント?に参加(というより潜入かな)するのは初めて
なので、とても楽しみです。
学生の頃は「勉強なんかしなくても死なないじゃん」
とか思ってたのですが。
最近読んだ本に、相手とのコミュニケーションについて
「言葉が話せるかよりも、伝えたい事があるかどうかの方が重要だ」
という主旨の文章がありまして、感心しちゃいました。
そうか036は今が学びたい時期なんだ、と思ったわけです。
・・・この情熱が仕事に行かないのが036流、なんて。





















